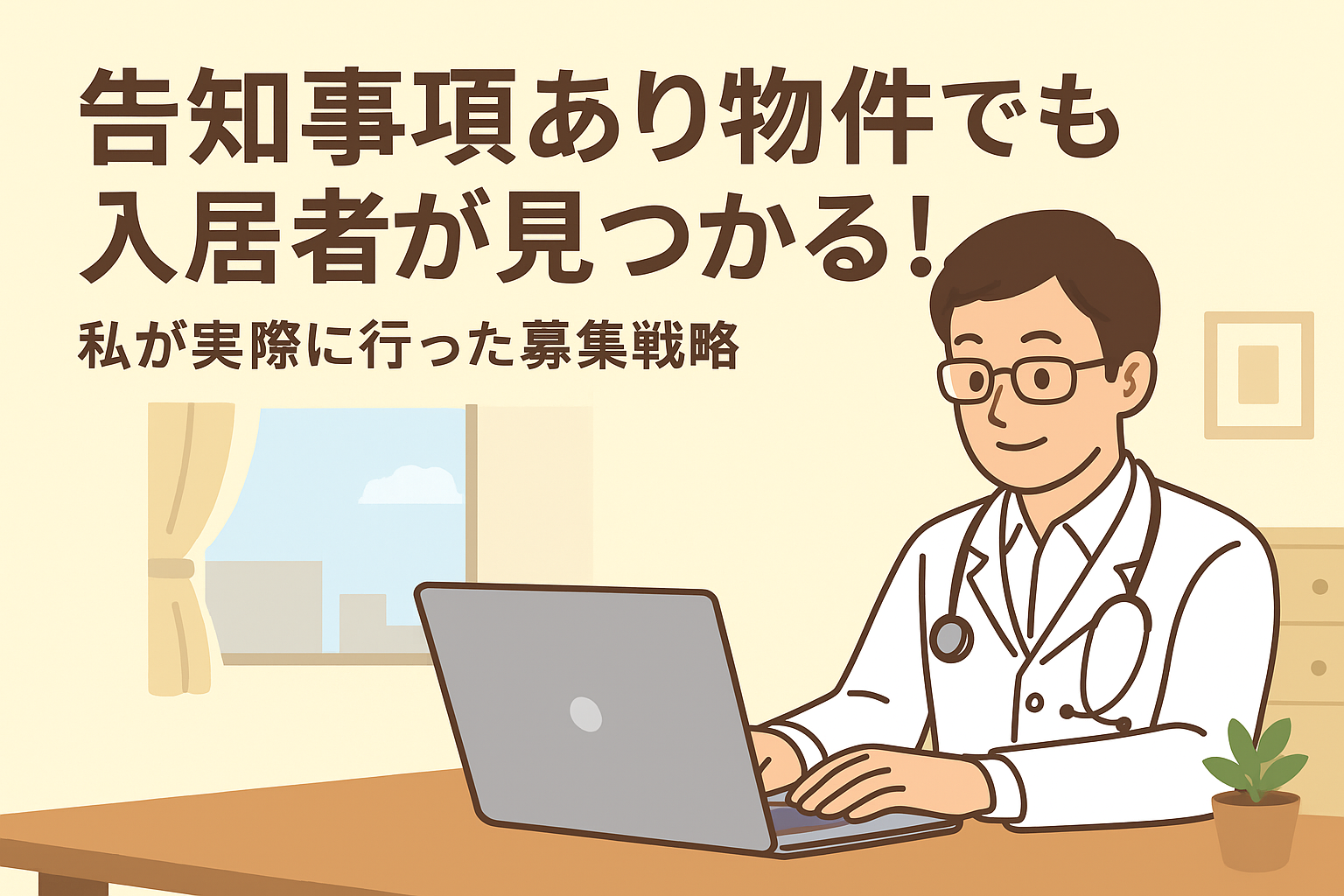こんにちは、看護師大家のたかのです。
今回は、**私が実際に所有している収益物件で起こった「騒音トラブル」**についてお話しします。
しかもこのトラブル、私が物件を購入する前から住んでいた入居者によるもの。
新オーナーとして引き継いだあとに、想像以上に対応が難しいケースとなりました。
今回はオーナーとしてどのように対応したのか、実際の事例をもとに記事にしていきます。
不動産賃貸業をしていると、避けて通れないのが「騒音トラブル」。
どんなに建物の防音性能を高めても、人が生活する以上、音の問題を完全にゼロにすることはできません。
そして、1番の問題は「音の感じ方は人によって大きく異なること」です。
「全く気にならない」という人もいれば、「眠れないほどつらい」と感じる人もいます。
私自身、複数の物件を所有していますが、その中の一棟で深刻な騒音トラブルが発生しました。
それは、夜間の痴話喧嘩が繰り返され、最終的には警察沙汰になったケースです。
この記事では、私が実際に経験したその一連の対応をもとに、
- 賃貸借契約における居住条件の基本
- 騒音が発生した際の具体的な対応ステップをまとめていきます。
同じように不動産を所有している方、これから賃貸業を始める方にとって、
トラブル対応の参考になれば嬉しいです。
賃貸借契約における居住条件について
まず前提として、入居者には「静穏に生活する義務」があります。
ほとんどの賃貸借契約書には、次のような条文が含まれています。
「入居者は、他の入居者や近隣住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」
「善良なる管理者の注意義務をもって建物を使用すること」
これはつまり、共同住宅における相互配慮の原則です。
お互いが静かで快適な環境を保つために、常識的なマナーを守る義務があるということです。
ただし、問題はここから。
実際には「どこからが迷惑行為か」という線引きが非常に難しいのです。
生活音なのか、騒音なのか――感じ方は人によってまったく違います。
そのため、私の物件では普段から以下のような工夫をしています。
- 入居時に「生活音に関する注意事項」を書面で説明
- 契約書にも「他の入居者に迷惑をかけないよう配慮すること」を明記
- 募集時点から「落ち着いた生活を希望する方向け」として入居者層を明確化
このように、トラブルが起きる前の予防がとても大切です。
とはいえ、私が経験したケースのように、前オーナー時代からの入居者がいる場合、
「契約内容の引き継ぎ」や「過去の人間関係」が絡み、対応が一層難しくなることもあります。
騒音発生時の対応(実際に私の物件で起きたケース)
ここからは、私が物件を購入した後に発生した実際の騒音トラブルについて具体的にお話しします。
①前オーナー時代から住んでいた入居者のトラブル
物件購入当初、その入居者(若い女性)はすでに長く住まれていました。
入居当初は特に問題の報告もなかったようですが、、、、、
引き継いだ後、他の入居者から「夜中の騒ぎがひどい」との連絡が入りました。
確認すると、夜間に交際相手との激しい痴話喧嘩が繰り返されており、
深夜5時頃に怒鳴り声が響くこともあったとのこと。
数回は我慢していた他の入居者も限界を迎え、「もう眠れない」「怖くて部屋を出られない」といった声が上がりました。
実際、数度にわたり警察が出動するほどの騒ぎにもなりました。
②まずは事実関係の把握
オーナーとして感情的に動くのは危険です。
私が最初に行ったのは、事実の正確な把握でした。
管理会社に依頼し、他の入居者へ

どの時間帯に、どのくらいの頻度で、どのような音がしていたか把握しないと
と考え丁寧にヒアリングを行いました。
結果、複数の入居者から同様の報告があり、
「一時的ではなく、継続的に発生している迷惑行為」であることが明らかになりました。
③内容証明郵便による注意喚起(1回目)
事実関係が整理できた段階で、内容証明郵便を送付しました。
1通目はあえて柔らかい表現にとどめ、
「他の入居者から騒音に関する苦情が入っているため、今後は十分にご配慮いただきたい」
という趣旨の注意喚起レベルの文面にしました。
この時点では、まだ改善の余地を期待していました。
内容証明にすることで、正式な注意を行ったという事実の記録も残ります。
④改善が見られず、2回目の内容証明を送付
しかし、残念ながらその後も状況は変わりませんでした。
夜間の口論が続き、再び警察が出動。
他の入居者からは「もう出て行きたい」という声まで上がり、実際に退去された方もいらっしゃいました。
そこで、2回目の内容証明ではトーンを変え、
「他の入居者の平穏な生活を著しく妨げており、重大な契約違反に該当する」と明記。
加えて今回は、連帯保証人にも同時に送付しました。
保証人に状況を知らせることで、社会的な抑止力を働かせる狙いもあります。
⑤最終通告と退去
それでも改善が見られなかったため、
3通目の内容証明で契約解除を前提とした最終通告を送付。
「2回の通告にも関わらず改善が見られないため契約を解除し、退去を求める」旨を明記し、
入居者と保証人双方に正式に通知しました。
結果として、そのかたは一定の期間を設けて自主的に退去されることになりました。
その後、物件の雰囲気は大きく変わり、他の入居者からも「静かになって安心した」との声が届きました。
⑥対応を振り返って
今回の経験で痛感したのは、
**「早めの対応」と「記録の重要性」**です。
最初の段階で曖昧にしてしまうと、他の入居者の不満や不安がどんどん膨らんでしまいます。
また、口頭注意だけでは証拠が残らないため、内容証明郵便のように形に残す対応が非常に有効です。

内容証明郵便は注意を書面で行ったという証拠が残るため言った、言わないということを防げます。
もうひとつ大切なのは、
「感情的ではなく、事実ベースで対応すること」。
相手を責めるのではなく、入居者全体の安心を守るための措置として、
淡々と手続きを進めることがトラブル解決の近道になります。
まとめ
騒音トラブルは、どんなに管理を徹底しても起こり得る問題です。
ただ、その対応の仕方次第で、
オーナーとしての信頼や物件の価値は大きく変わります。
今回のケースで学んだことは、
- 感情的にならず冷静に事実を確認する
- 管理会社と連携して早期に動く
- 内容証明などの書面で段階的に注意を行う
- 必要に応じて保証人も巻き込む
という4つの基本です。
そして何より、オーナーの姿勢が問われます。
物件の価値は「建物の状態」だけでなく、
「安心して住める環境づくり」によっても決まります。
今後も、入居者全員が穏やかに暮らせる環境を守るために、
オーナーとして誠実に対応していきたいと思います。
 夜勤を手放して見つけた、小さな幸せと大きな自由
夜勤を手放して見つけた、小さな幸せと大きな自由