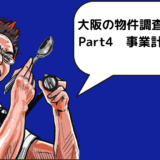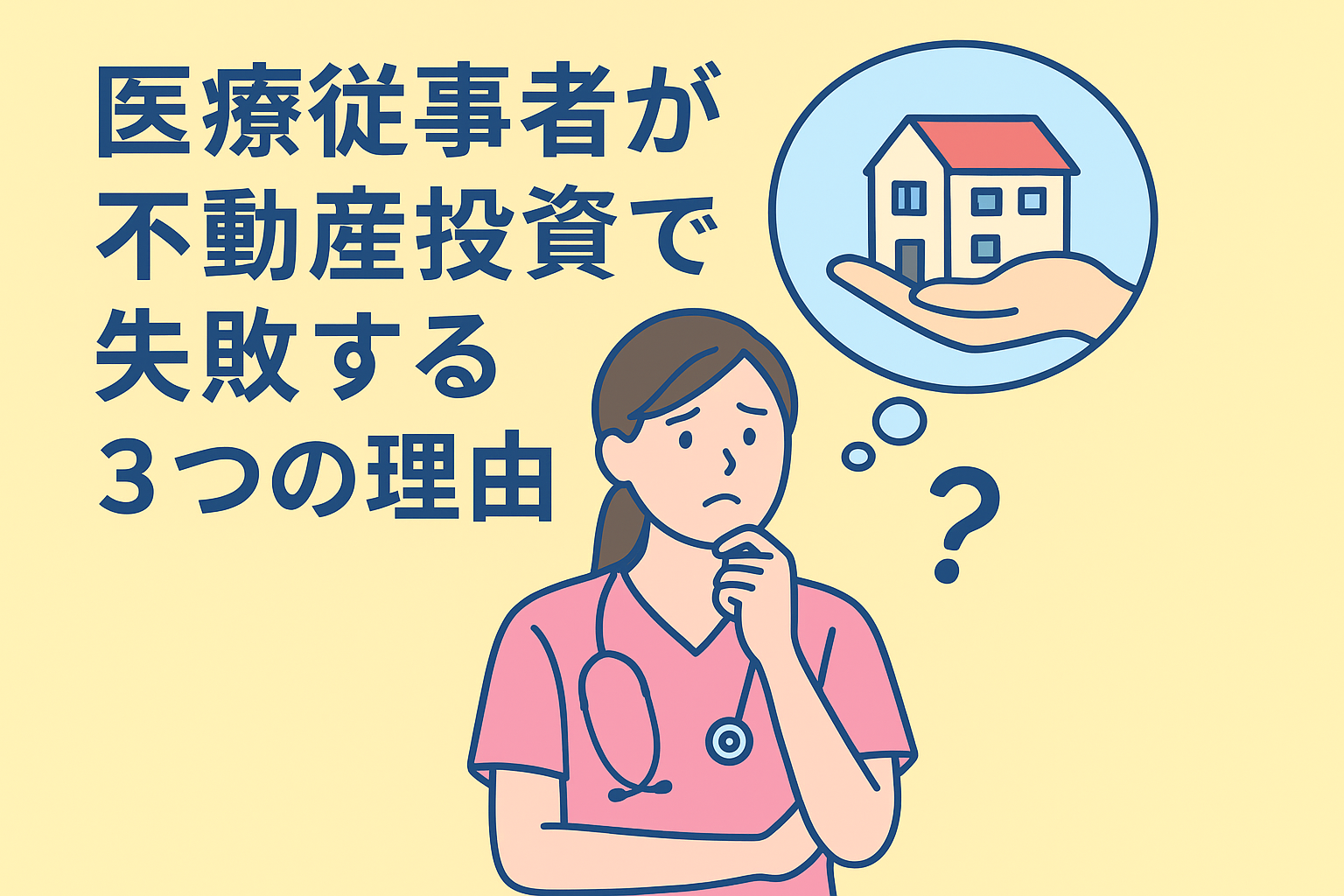こんにちは。
看護師大家のたかのです。
今日は不動産における積算評価について解説します。
積算評価は、不動産投資を行う上で非常に重要な要素。
融資の場面でも必ず登場しますので、ぜひこの機会にしっかり学んでいきましょう。
👉 私の自己紹介はこちらのプロフィール参照してください。
不動産の積算評価とは?
積算評価とは、不動産の「再取得にかかる費用」を基に価値を算出する方法のことです。
つまり、「その土地や建物をもう一度つくるとしたら、いくらかかるのか?」という考え方で評価します。
この評価は、金融機関の融資判断や税務評価などで活用されるため、不動産投資家にとって避けて通れない指標です。
✅ ポイント:積算評価は“実質的な価値”を示すもので、市場価格とは必ずしも一致しません。
積算評価の基本構成
積算評価は主に「土地」と「建物」の2つに分けて計算します。
ここが大事なので2回言います。「土地」と「建物」です!
① 土地の評価
土地の積算評価では、
- 路線価
- 固定資産税評価額
といった公的な基準をもとに算定します。
たとえば商業地域の土地は住宅地より評価が高くなり、
逆に形が悪い土地や接道が悪い土地は減額されます。
>土地価格の調べ方はこちらを参照:[土地の価値ってなに?絶対知っておきたい土地価格について]
② 建物の評価
建物は、「再建築費用(新築時のコスト)」をベースに評価します。
以下の国交省サイトでは、おおむね13万円/㎡前後が参考値です。
(国交省 建築着工統計)
建物の構造によっても評価が変わります:
| 構造 | 法廷耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| RC造(鉄筋コンクリート) | 47年 | 評価が高い |
| 重量鉄骨造 | 34年 | 比較的長い |
| 木造 | 22年 | 減価償却が早い |
| 軽量鉄骨造 | 19年 | 木造に近い扱い |
築年数が経つほど、減価償却によって評価額は下がります。

法定耐用年数を超えると基本的に建物の価値は無くなります。これは非常に重要な考え方なので押さえておきましょう!
③ 付帯設備や外構の評価
積算評価では、駐車場・フェンス・庭などの外構も含まれます。
それぞれに再建築費用があり、加算対象となります。
ただし設備ごとの評価は細かいので、税理士への相談がおすすめです。
積算評価の計算方法
計算式は次の通りです:
積算評価額 = 土地評価額 + 建物評価額 − 減価償却額 + 付帯設備評価額
土地の路線価・固定資産税評価額を基に土地価値を求め、
建物は再建築費用から経年劣化分を差し引きます。
最後に外構の価値を加えて、全体の積算評価額が完成します。
(※減価償却費の考え方については、後日詳しく記事にします)
積算評価が使われるシーン
- 不動産売買
市場価格が変動しても、積算評価は“実質的価値”を確認する際に有効です。 - 金融機関の融資判断
銀行は「担保価値」を見る際に積算評価を重視します。
特に築古物件の融資では、積算評価が基準になることも多いです。 - 税務申告や相続評価
固定資産税や相続税評価の根拠としても使われます。
積算評価の限界
積算評価はあくまで物理的価値の指標です。
市場の需要や地域人気は反映されにくく、
都心部などでは「積算評価<市場価格」となることが多いです。
一方で、郊外や築古物件では「積算評価>市場価格」となるケースもあります。
築古物件について過去のこちらの記事を参照してください。築古一棟不動産のメリットとデメリット【初心者にもわかりやすく解説】
積算評価と市場評価の違い
| 比較項目 | 積算評価 | 市場評価 |
|---|---|---|
| 基準 | 再建築費用・物理的価値 | 実際の取引価格・需要と供給 |
| 用途 | 融資・税務 | 売買・査定 |
| 反映される要素 | 建物構造・耐用年数など | 立地・人気・需給バランス |
| 価格傾向 | 安定的 | 変動が大きい |
どちらか一方ではなく、両方のバランスを見て判断することが大切です。
まとめ
積算評価は、土地・建物の物理的な価値を算出するための重要な評価方法です。
融資や税務の現場で使われることが多く、不動産投資を始めるなら必ず理解しておきたい知識です。
ただし、市場価値とのズレを理解し、積算評価+市場評価の両面から判断するのがベストです。
特に築古物件を検討している方は、この「積算評価」を軸に物件選定をしてみてください。
次回は「築古一棟不動産の減価償却」について解説します。
 夜勤を手放して見つけた、小さな幸せと大きな自由
夜勤を手放して見つけた、小さな幸せと大きな自由